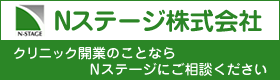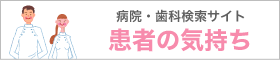生活習慣病が気になる方へ
そもそも生活習慣病とは、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常(高脂血症)、痛風といった、生活習慣や体質によって起こる慢性疾患のことをいいます。
生活習慣病は無症状な事が多く、また病気が進むと様々な合併症を引き起こします。特に心臓病、脳卒中、大動脈の病気、腎臓病などの重篤な病気のリスクが高まります。治療については、生活習慣やライフスタイルを変える事から始め、食事の取り方や内容、運動の種類や量、嗜好品(たばこやお酒)、睡眠時間、ストレス管理に至るまで、幅広く考えていく事が必要となります。
主な生活習慣病
高血圧
血圧が高い状態が続く事で血管の壁に圧力が掛り、その結果血管を傷めて次第に血管が硬くなり動脈硬化へとつながります。
高血圧の原因は特定されていませんが、遺伝的要因と食生活(塩分の高い食事)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、または運動不足や精神的なストレスなどの環境的要因が重なって引き起こされると考えられております。
糖尿病
糖尿病は、膵臓から出る、血糖値を下げるホルモン(インスリン)の働きが弱かったり、量が少ないなどの原因で血糖値の調整ができずに、高値になってしまう病気です。高血糖が続くと、糖尿病合併症(神経障害・網膜症(眼の病気)・腎臓病)や、脳梗塞、心筋梗塞などを引き起こす可能性もあります。
脂質代謝異常(高脂血症)
脂質代謝異常(高脂血症)とは、血液中を流れるコレステロールや中性脂肪などの脂質成分が適正な範囲を超えて上昇した病態のことを言います。食事から取り込んだ脂肪分は腸管から吸収されて、肝臓で再処理を受けたあと、血液を通して全身へ運ばれ、エネルギー源あるいは細胞を造る材料として適切に利用されます。この収支バランスが崩れると血液中に脂質成分が過剰に溜まった状態です。
高尿酸血症(痛風)
高尿酸血症(痛風)とは、足の親指のつけ根などの関節に炎症を起こして、強い痛みを伴う病気です。血液中の尿酸値が高いと、関節に尿酸の結晶がたまり、突然強い炎症を起こします。
発作的な痛みの症状がおこるため、痛風発作と呼ばれています。発作が続くと足首や膝の関節までも痛み始め、発作の間隔が次第に短くなり、関節を破壊していきます。30代、40代男性での発症が多く、女性は全体の1~2%くらいの割合で、男性に圧倒的に多い病気です。